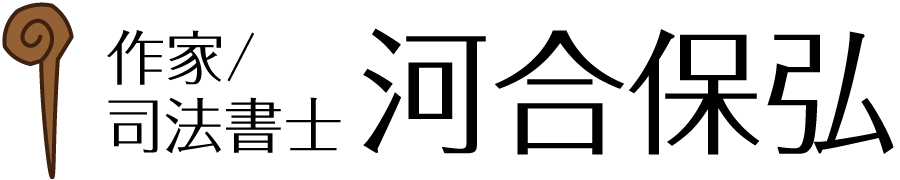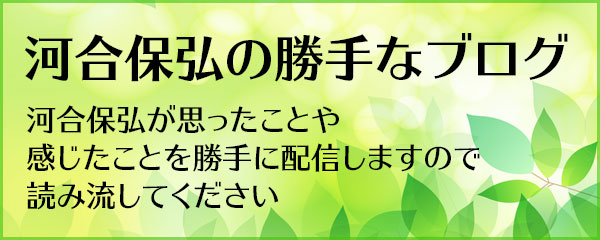天下の悪法“遺留分”を回避せよ! “How to Avoid Bad Law!”
第1回:「天下の悪法」とは?~その1
再び連載を開始させていただきます。
なお、この連載は、私がアップした後に、監修をお願いしました司法書士の日下淳さんの記事「『モノ』を言う‼闘う若手司法書士からの進言」を毎回連続でアップするという形式で進めたいと思っておりますので、続けてお読みいただければと思います。
さて、このタイトルは、1965年にアメリカで発売されたベストセラー「How to Avoid Probate!(検認手続きを回避せよ!)」へのオマージュです。
私の連載小説「田和家の一族」の第19・20回にも登場していますが、この本の著者であるノーマン・デイシー(Norman Dacey)氏は、弁護士などの法律専門家ではなく、不動産業を営む一般人でした。
アメリカの相続制度は、人が死亡すると、遺言の有無に関わらず裁判所による「Probate(検認手続き)」が必要で、そのために要する手間と費用が不合理ではないかとデイシー氏は考え、相続とは別の制度である「living trust(生前信託)」をしておくことによって、Probateが回避できるのではないかと指摘し、これを著書にまとめたところ、大ベストセラーとなりました。
しかし、当時の弁護士をはじめ法律関係者は、「それは脱法行為だ」と決め付けて痛烈にデイシー氏を批判し、訴訟も数多く提起されたそうです。
それは当たり前のことで、当時のアメリカの弁護士は、Probateを代理で行って多額の報酬を得ることが一種の利権になっており、ましてや新しい法律の使い方の話を、法律家でも何でもない一般人が言い出したのですから、まさに「沽券に関わる」ことであり、それはさぞや激烈な攻撃であったものと想像できます。
それでも、living trustを国民のために普及させたいと考えたデイシー氏は最後まで初心を曲げることなく、やがて国民は自らの意思で積極的にliving trustを選択するようになり、50年以上が経過した現在、もう当然のようにliving trustはアメリカ国民の常識となりました。
私は、法律家ではないデイシー氏が、当時の法律家が誰一人として気付かなかった「信託」という仕組みを財産承継に活用しようと考えたことは、とても大きな意味があると思っています。
さて、我が国に目を転じてみますと、現在でもまだデイシー氏登場前のアメリカと、時代は全く変わっていないのではないかと思います。
最近では一般市民の間で信託を使うケースも少し増えてはきましたが、まだその本質を理解して活用している人は専門家も含めてほとんど皆無ですし、未だに「民法上の相続」が財産承継の基本だと強く思い込んでいる向きが大多数です。
そして、その「民法上の相続」が、国民の誰もが納得し、受け入れられている制度であるならともかく、これが極めて問題の多い制度であることに、意外と気付いている人が少ないということが、実は最大の問題なのではないかと私は考えています。
ただ、一般国民が現行制度に問題があるという事実に気付くのは、その人が実際に問題に直面し、大きな被害を受けた時であり、その段階では既に「被相続人」と呼ばれる財産の所有者、すなわち「本当の意味での被害者」は死亡しているのですから、その時点では手遅れで、諦める以外の選択肢はありません。
ここで「本当の意味での被害者」と敢えて書きましたが、その意味を説明するために、質問をさせていただきましょう。
さて、あなたの財産は誰のものでしょうか?
それはもちろん、財産を持っているその人自身、すなわちあなたのものですよね。
では質問を変えます。
あなたの親が持っている財産は誰のものでしょうか?
もちろん、親の生存中は、当然に親のものですよね。
ではその次の質問です。
親が亡くなったら、親の財産は誰のものでしょうか?
実は、ここで多くの人が間違えるのです。
ほとんどの人は、こう答えるでしょう。
「それは相続財産だから、相続人みんなのものでしょう。」
これ、実は間違った答えなのです。
正しい答えを申し上げます。
それは「確かに、親が何の意思表示もしていなければ、一応は自動的に相続人みんなのものになります。しかし、親が何らかの意思表示をしていて、かつ書面上での決め事をしていた時には、まずはその内容に従うことになります。」です。
ここで言う「書面上の決め事」には、遺言だけではなく、生命保険などの各種の契約行為も含まれますが、ここではまず遺言に絞って考えてみましょう。
そうです、遺言書が1枚あれば、亡くなった人の財産は、相続人であるか否かには関係なく、遺言書に書かれている人や法人が取得することになり、決して自動的に相続人みんなのものになるのではありません。
ですから、本来であれば誰もが遺言をしておけば、財産は自分の思う通りに承継させることができ、「争続」などという事態も生じませんし、親に対して悪行を重ねた子(親不孝者)や、籍だけは残っていても実質的には完全に関係が破綻している配偶者(居座り配偶者)などに遺産を取られてしまって、死亡した人の意思は生かされず、かつその人のために誠心誠意尽くした人が馬鹿を見るというような心配はないはずです。
しかし、これは本当に残念なことなのですが、我が国の民法には「遺留分」という、とんでもない制度、まさにこの連載のタイトルにある通りの「天下の悪法」が存在していますので、そうはいきません。
現在の遺留分制度については、次回ご説明いたしましょう。

※天下の悪法として有名な、17世紀に徳川綱吉が作った「生類憐みの令」ですが、下記URLの記事などを読むと、動物愛護の精神や人権尊重など、どうやらそれなりに良い部分もあったようです。
それなら、親不孝者や居座り配偶者を除いて、大多数の国民にとって何一つ良いことがない遺留分制度よりはマシなのかも?と思ってしまいます。
https://edo-g.com/blog/2015/12/shorui_awaremi.html