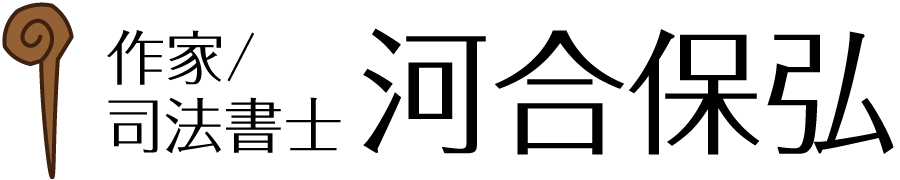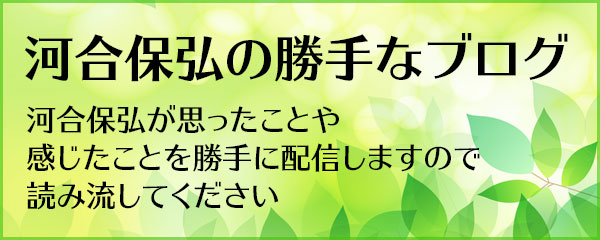鴛鴦(えんおう)“OSHI-DORI”第3章 株式会社スイートパラダイスの巻
第3話:元カレ
その日の夕方、真凛は優也を自宅事務所に招いていた。
「マリンさん、暫くぶりだね。この部屋に来させてもらえる日を心待ちにしていたから。」
真凛も実は嬉しかったのだが、いつものように嫌味な事を言ってしまう。
「私たち、あくまでも仕事の上での関係だから、仕事がないと、ここでは会えないのよ。」
「では、仕事をくださった方に感謝しよう。砂川光一さん、大学時代の同級生だってね。どんな関係だったの?」
真凛は一瞬たじろいでしまったが、何とか気を取り直して言う。
「どんな関係って、ただの同級生だよ。」
頬を赤くしてコーヒーカップの底の砂糖を掻き混ぜる真凛の仕草から、優也は察してしまったようだが、敢えてそのことは口にするまいと思っていた。
何となく気まずい雰囲気になるのを断ち切るため、優也は事前に送って貰っていた書類や決算書を見ながら、先に話を始めた。
「確かに、かなり資金繰りが厳しくなっているから、今回の出資の話は有難いことではあると思うな。ただ損害賠償請求は一段落しているみたいだし、あとは風評被害だけだから、支援なしでも生き残れる可能性はあるかも知れない。ここ半年くらいが勝負どころになりそうかな。」
優也の、さすがはプロといった的確な分析に、真凛は感心しながら、この事案は光一への気持ちを忘れて、純粋に仕事として取り組まなければと決意していた。
「ところで、株式会社ブラックペッパーを調べてきたんだけど。」
「優也さん、もう調べてきてくれたのね。」
「うん、確かに勢いのある会社で、既に何社かをM&Aで買っているみたい。」
「どんな会社を買っているの?」
「分かっているところでは、同業者を1社、カレーの缶詰とかの加工食品を作る会社を1社、それからインドカレー屋さんを1社かな。」
「辛いもの系ばっかりで、甘いものを扱う会社はないみたいね。」
「そうだね、果たして食中毒事件で困っているS社を善意で助けようとしているのか、あるいは一時的にS社の価値が下がったところで安く買収しようとしているのかだな。」
「今回はM&Aという話はないみたいだけど?」
「最初は支援とか提携とかから入って、最終的にメリットがあると思えばM&Aに進むというのが、この手の会社の常套手段だからね。おそらくB社側も様子を見ているんだろうな。」
優也の情報によると、B社の経営者の黒川源二は、元は胡椒などの香辛料を売る商店街の中の乾物屋の息子だったが、商才があるのか事業を拡大し、今では南米やアフリカからのルートを使って各種の輸入食材を扱う、ちょっとした商社になっており、S社とも香辛料とかで少しだけ取引があって、S社の取引先や、ヨーロッパからのチョコレート輸入ルートにも魅力を感じているらしいという。
真凛は、光一からの手土産で貰ったチョコレートを食べながら言う。
「辛いものを扱う会社が、チョコレートの会社に興味を持ったということなのね。」
「確かに輸入ルートなどは同じ部分もあるだろうから、B社にとってはメリットがあるし、S社にとっても悪くない話なのかも知れないな。」
「ただ、その黒川っていう社長の腹が黒くなければの話だよね。」
「その通り。そのあたりを探るのは難しいので、まずはS社の関係者の人たちがどう考えておられるかをヒアリングしてからかな。」
「そうね。昨日の砂川君の話を聴いていて思ったんだけど、砂川君は会社を継ぐ気がなくて、お父様である社長さんは今は気持ちが沈んでいてB社からの申し出に積極的ではなくて、それに砂川君が後継者にと推薦するお姉さんはご両親との関係が微妙ということだから、結局どうしたらいいのか、当事者が分かっていない感じなのね。それに社長の弟さんや昔の同級生さんが役員になっておられるから、彼らの考え方もそれぞれにあるでしょうし、なかなか大変なヒアリングになりそうよ。」
「そうだね。さっきマリンさんが言っていたように、社長の弟さんや専務さんが万に一つでもB社に協力するようなことになれば、たちまちS社は乗っ取られてしまうんだから、慎重にヒアリングしないといけないよね。」
「今回は男性ばっかりだから、やっぱり私が頑張った方がいいのかな?」
「そうだね、マリンさんには人の気持ちを和らげる力があるように思うから、僕は後ろに回って数字や理屈の部分だけ受け持つことにするよ。」
「何だかプレッシャーだわ。」
「僕たちがガッチリ組めば大丈夫。何よりも今回の案件は、マリンさんの昔の同級生からの依頼だから、最初から一定の信頼関係があるというのは強みだよね。」
こうして、優也が協力してくれることに決まったので、早速真凛は光一に電話をして、明日の午後からS社を訪問することになった。
しかし、優也は真凛と光一の会話に聞き耳を立てていたようで、真凛に言う。
「マリンさん、砂川光一さんのこと、コーちゃんって呼んでたんだ。」
真凛は、ついうっかり仇名が口に出てしまい、慌てて言い直したのを優也にしっかり聞かれていたようで、しまったと思った。
「あっ、いや、その、あの、大学時代は同じサークルとかグループとかで一緒だったので、ついつい昔の事を思い出してしまっただけで、決して他意はないのよ。分かって。」
優也は、慌てる真凛を見て、これは間違いなく“元カレ”からの依頼だと確信したので、逆にますます気合を入れてかからなければならないと思うのであった。
優也は、真凛のマンションからの帰り道、いろいろと妄想している。
あの天真爛漫な真凛の大学時代はどんな子だったのだろう。
その真凛の元の彼氏って、いったいどんな人物なのだろう。
大学時代の同じサークルやグループって、いったい何だったのだろう。
真凛と彼氏とはどこまで関係が進んでいたんだろう。
で、どうして別れたんだろう。
そして、今になって真凛に仕事を依頼してくるというのは、いったいどういった趣旨なのだろう。
何か別の目的があるのだろうか?
これまでの真凛のイメージから、彼氏が居るという状況をどうしても想像できない優也であったが、真凛も26歳なのだから、全く異性と付き合った経験がない訳がないのだろう。
いろいろと考えるうちに、明日に会う予定の砂川光一に対して、激しい闘志が沸き上がってくる優也であった。
(つづく)

※B社で取り扱っている色々な種類のスパイスさんたちね! マリンの食卓を彩るために世界中から集まってきてくれたなんて、とっても素敵!!