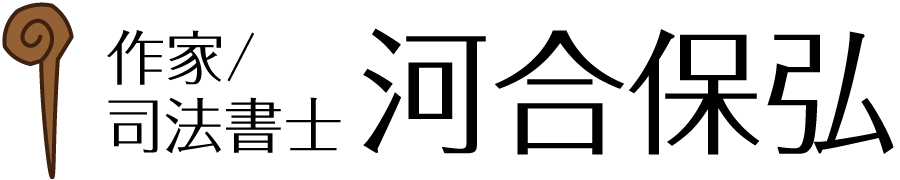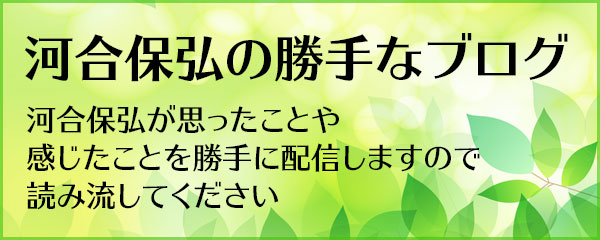鴛鴦(えんおう)“OSHI-DORI”第3章 株式会社スイートパラダイスの巻
第2話:砂川君と緑野さん
「ところで砂川さん。」
早速に苗字で砂川光一を呼んでみた緑野真凛に、光一は戸惑っている。
「うーん、やっぱり違和感あるよな。親父も砂川さんなんだし、ややこしくないかい?」
「そうね、じゃあ同級生らしく、砂川君にするわ。」
こうして、砂川君と緑野さんとの会話が始まった。
「ところで、砂川君自身は、これからどうしたいの?」
真凛の問いに、光一はゆっくり答える。
「俺、いや僕って言った方がいいよね。僕はチョコレート自体には全く興味がないし、この仕事を長く続ける気持ちは最初からないんだ。でも、親父は食中毒事件の処理に追われるようになって以来、すっかり意気消沈しちゃって、もう辞めたいとか言ってはいるけど、元々はチョコレートを扱うことに誇りを持っていたし、できることならこの仕事を続けさせてやりたい。と言っても、親父ももう57歳だからね、いずれは引退しなければならないんだろうけど。」
「お父さんは、今回のB社の申し出については、どう言っておられるの?」
「B社の黒川という社長とは気が合わないみたいで、もし業務提携とかになったら僕に社長を交替して欲しいって。でも僕は後継者になる気がないから。」
「もし砂川君が後継者にならないとしたら、会社はどうしたらいいと思う?」
「実は、僕には真美っていう4歳上の姉がいて、一度結婚して九州に行って、今は離婚して子連れでこちらに戻ってきているんだけど、姉はパティシエという職業だから、会社の後継者には向いていると思うんだ。」
「パティシエ!私の憧れの職業じゃない!!じゃあ、お姉さんが会社を継がれるという方向でいいのね?」
「いや、ところがね、結婚と離婚のことで両親と険悪な関係になっていて、今はそんな感じじゃあないんだよ。」
「親子関係かぁ、難しいわね。じゃあ今の時点では、砂川君は会社を継ぐ気持ちはなくて、お姉さんに継いでもらいたいけど、親子関係に問題がある。支援を申し出てきたB社の思惑や経営者の人となりとかは分からないし、提案書の内容も難しくて理解しづらい、ということね。」
「そうだね、簡単に言うと、親父の希望を叶えながらも、僕は早く抜けたいってことさ。」
その後、真凛は、光一から示された書類をチェックし始めた。
「何だか横文字が多くって、とっても分かり難い書類だわ。この手の文書は、おそらくコンサルタントみたいな人が作ったのでしょうね。」
「そうだろ。白状すると、実は以前に自分で会社をやっていた頃、コンサルタントから出された横文字だらけの変な書類に署名しちゃって大変なことになった経験があるので、とっても警戒しているんだ。」
「砂川君も苦労したのね・・・。」
「その頃は突っ張ってたからね。意味の分からない横文字も、カッコ付けて読めてるフリをしてしまって・・・。本当にいろいろな経験をさせてもらったよ。」
真凛は、携帯電話の機能を使って、何度もビジネス英語や金融用語らしき言葉の翻訳をし、ようやく書類の確認を終えた。
「とりあえず全部チェックしたけど、この書類の内容だけで言うと、意外と中身は薄っぺらくて、要はB社がS社に対して出資をして株主になり、取締役を二人入れて経営に関与させてくれという程度のことみたいで、怪しい部分はないようね。ところで、今の会社の役員さんの構成はどうなっているの?」
「親父が社長で、親父の弟の良治叔父さんが取締役経理部長、それから親父の大学からの友達で、創業の時から経営を手伝って貰ってる白岩哲雄さんっていう人が専務取締役だから、その他に二人入れろってことか。」
「良治叔父さんと白岩専務は、どんな感じの人なの?」
「良治叔父さんは本当に大人しくて真面目一筋みたいな人だよ。税理士試験を20年以上も受け続けてダメで、最初は親父が会社に入れてあげたって感じだったらしいんだけど、今では経理を一手に引き受けてくれているから、会社の数字については一番詳しいんじゃないかな。白岩専務は親父の大学時代の同級生で、親父が15年ほど前にサラリーマンを辞めて会社を立ち上げた時から手伝ってくれていて、輸入の事務とかにも詳しいし、実は親父は経営には疎いので、専務が実質的に経営をしているという感じなんだよ。」
「株の持ち方は?」
「今は親父が130株と叔父さんが20株、それから白岩専務が50株の計200株だよ。」
「そこにB社が200株出資してくるから、とりあえず半分はB社の権利になっちゃうのね。そうすると怖いのが、B社と白岩専務さんが組めば株数も取締役の数も過半数になってしまうし、さらに叔父さんも組めば株数が3分の2以上になって、実質的に乗っ取られてしまうことになるわ。」
「白岩専務も良治叔父さんも、そんなことはしないと思うけど。」
「もちろんそうでしょうけれど、あらゆるリスクを事前に把握してから判断するのが経営の基本なんだよ。」
光一は、5年ぶりに会う真凛の変わりように驚くばかりである。
真凛は言葉を続ける。
「おそらく、良治叔父さんも白岩専務さんも、それぞれに考えるところがあるでしょうから、全員で一緒にではなくって、一人一人と個別に会って話を聴きたいの。砂川君は全員と人間関係はあるのよね?」
「そうだね、あの人たちから見たら、僕は社長の頼りない息子ってことだろうから、可愛がってはもらってるし、親父が同席するよりは僕が一緒に会う方がいいかも知れないね。」
「では個別に会えるように手配しておいてね。それから、おそらく資金繰りとかも大変になってきていると思うので、事前に会社の経営内容とかを見てから、外部からの支援については判断すべきと思うの。そこで私の信頼できるパートナーである中小企業診断士の青芝優也さんに協力して貰いたいんだけど、構わないかな。」
「あぁ、噂に聞く凄腕のパートナーさんね。もちろん、お願いするよ。近々に二人で会社に来てくれるかな。マリンちゃん、じゃなかった、緑野さんのパートナーさん、お会いするの楽しみだな。」
「パートナーと言っても、あくまでも仕事の上だけで、プライベートでは一切何の関係もないからね。」
真凛は、余計な事を言ってしまったと思ったのか、またコーヒーカップの底をスプーンで掻き混ぜ始めている。
光一は、その仕草の意味は分かっていないようだが、真凛の表情を微笑ましく見つめていた。
(つづく)

※これが光一君の会社で輸入している、チョコレート製品の原料さんよ!これが色々なチョコレートのお菓子になって、マリンに食べられてくれるの!!