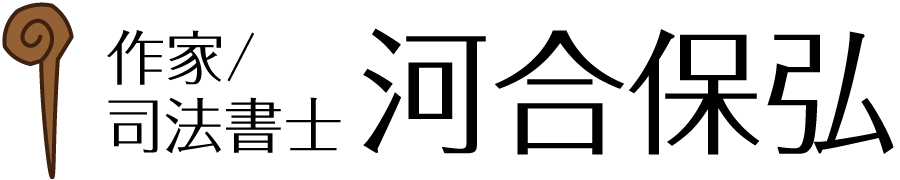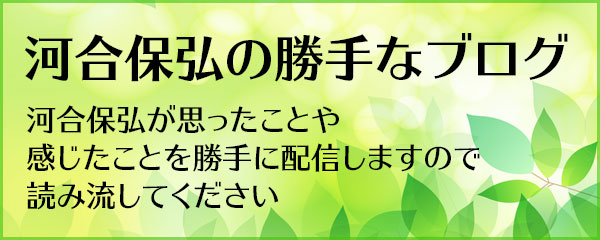震災復興&歴史発掘ファンタジー
「ストロベリーランナー ~亘理伊達開拓団からのメッセージ~」
第13回:苦難の道
明治3年4月。
第1回亘理伊達開拓団として移住する約250人は、ついに蝦夷地、亘理伊達家の新たなる“領地”とされた有珠地区(現代の伊達市)に足を踏み入れた。
全く自然のままに木や草が繁り放題になっている無人の原野、今は爽やかに晴れているが、やがて冬になって一面が銀世界になるのであろう。
「ここが我らの新天地、新しい亘理の地だ。いざ切り開かん!!」
家臣の誰が発したでもない号令に、開拓団は一斉に勝鬨を挙げる。
本来なら号令を発するべき家老の田村顕允は、第1回の開拓団には参加せず、亘理に残っているのである。
実は、その頃の亘理では、開拓団とは別の問題が勃発していたのであった。
領主・伊達邦成は満足そうに家臣たちに目をやっているが、その心の中にある恐怖や不安を誰よりも理解している。
何しろ、全く知らない土地が突然に自分たちの住み家とされ、そこには先住民であるアイヌの人々が既に長らく暮らしているのだ。
しかも、今の開拓団には先住民を支配できる権限などはなく、形の上では“亘理伊達家の領地”とはなっていても、あくまでも“住まわせていただく”という立場なのである。
その上、武家ばかりで農業の経験などほとんどない開拓団に与えられた土地は、まさに何もない原野、本当にこれが耕作地になるのだろうか。
そんな時、開拓団の心の支えになっていたのが、亘理伊達家の初代当主であり、あの伊達政宗の従弟でもあった伊達成実の存在であった。
「前に進め!」
開拓団は、苦しい時、この言葉が成実公から発せられていると思うようにしていた。
伊達邦成は別筋の伊達家から迎えられた養子であり、成実の直系の子孫ではないが、その心意気は栄光ある伊達家共通のものとして理解していたのである。
開拓団の一行に、邦成は訓示する。
「開拓の事業は戦とは異なり、骨を惜しまず勤労すれば必ずや報われるものである。」
確かに、戊辰戦争では、たまたま敗軍側にあったために敗れたのであり、必ずしも亘理伊達家の面々に落ち度があったのではないのであるから、主君のこの言葉には誰もが納得するのであった。
しかし、邦成の次に訓示は、開拓団にとってはなかなか難しい課題であるのかも知れなかった。
「我々の開拓が成功裏に終わるか否かの分かれ目と思われる要点はもう一つある。それは先住者であるアイヌの人たちを尊重し、心を通わせ、真の仲間となることである。我々が来たことが彼らにとっても益になるようにしなければならぬ。十分に心せい。」
そう言われても、生活習慣が全く異なっており、言葉すらほとんど通じないアイヌの人たちと、武家の生活しか知らない開拓団の面々とが心を通わせるのは容易ではないのだ。
アイヌの若き首領・ウテルケは、亘理伊達開拓団が来ること自体には理解を示していたが、言葉が通じないと侮って、先住民に対して差別的な言葉を使う者たちを許せなかった。
実は、ウテルケは戊辰戦争以前に、開拓地の近くに昔からあった有珠善光寺の僧侶・瑞覚の付き添いで江戸に行って仏教を学んだことがあり、金成春泰(かんなり・はるやす)という和名も持っていて、先住民の中で唯一、開拓団の話す言葉が全て理解できるのであるが、彼は敢えてそれを隠していたのである。
もちろん、ウテルケは争いを望んでいたのではないので、一部の不心得な開拓団の者が発する差別的な言葉を、仲間に通訳して知らせることはしなかったが、何度かは両者が衝突することもあり、時には武術にも長けた彼が、双方の不心得者を力で押さえなければならないこともあった。
邦成は、あらゆる事柄が初めての経験であり、それに戸惑う開拓団を取りまとめるには、一日も早く開拓の第一歩を記するため、期限を切って目標を作るのが良いと考え、到着してから僅か10日後の4月17日を開拓開始の式典の日と定めた。
そして開拓団は、昼夜を徹して50軒以上の仮小屋を建て、何とか開拓の根拠地を作り上げたのであるが、誰の目から見たとしても、前途は多難であろうと思われた。
(つづく)

時代劇部分登場人物紹介(第13回)
ウテルケ(和名・金成春泰 かんなり・はるやす)
亘理伊達開拓団が行った紋別地区のアイヌの若き首領で、最初は先住民を代表して邦成たちと対立するが、やがて協力関係を結ぶことになる。
架空の人物である。