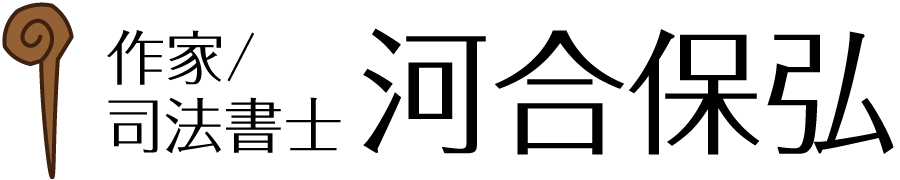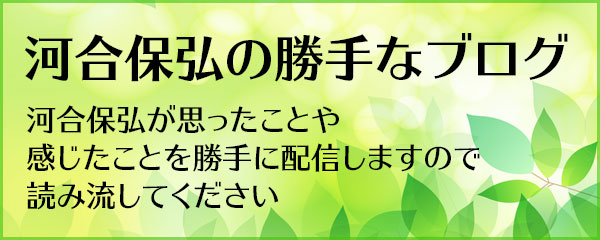震災復興&歴史発掘ファンタジー
「ストロベリーランナー ~亘理伊達開拓団からのメッセージ~」
第12回:汚泥の中から
千草繁明が丹精込めて育てた、いわば繁明の命とも言える大切な苺畑は、押し寄せた海水に晒されて、影も形もなくなってしまっていた。
つい最近まで、この浜吉田地区は立入禁止区域になっており、住民ですら入ることができなかったのだ。
ようやく傷が癒えて、この場所に戻ることができるようになった繁明は、呆然と立ち尽くしている。
「もうダメなのか。」
少し前まで畑があったらしい場所に立って、大きな溜息をつく繁明。
一度海水に浸かってしまうと、その土地は全ての土を入れ換えでもしない限り、もう耕作は不可能であり、仮に土を入れ換えたとしても、必ず元の肥沃な土地に戻るという保証はないのである。
それに、繁明にはそんな大きな土壌入れ換え工事をするだけの経済的余裕はないし、そもそも既に66歳になっている繁明が、今から自分の力で何かをスタートするなどということは、物理的にも精神的にも到底無理な注文なのであった。
その時、繁明は、足元の汚泥の中から、小さな苺の若葉が頭を出しているのに気付いた。
「そうか、生きていたのか。わしも何とか生きているよ。」
繁明は、その生命力に感動した。
だが、可哀そうにも、この若葉は、ここでは絶対にこれ以上は成長することができない運命にあるのだ。
そして、顔を上げてみれば、見渡す限り海水の混じった汚泥と瓦礫が見えるばかり。
「もうこの場所は使えないだろうな・・・。しかし、わしには苺造りしかない。」
繁明は、その苺の若葉を、何か大きな恐怖のようなものから救い出すが如くに拾い上げ、苺畑の復活の日まで大切に持ち続けることにした。
3.11、津波に呑まれた繁明がしっかり手に掴んでいた苺の苗を廃物として捨てられてしまって以来、本当に久しぶりに触れる苺であったから。
その頃、田村正章は大学院の研究室に居た。
3.11には高設水耕栽培の指導のために北海道伊達市に行っており、そのまま数週間の滞在予定であったが、震災の報道を見てすぐに故郷に戻ってきたのである。
金成泰春が、被災地では交通が遮断されることを予測して、買ったばかりの自分の車を提供してくれたのだ。
いつ返せるか分からないことを気にする正章に、泰春は言った。
「俺には農協の車があるからいいんだよ。どのみち亘理では車も被災してるだろうから、1台でも多い方が何かの役に立つだろう。」
正章は、泰春と先祖たちの、時を超えた深い友情に、心から感謝するのであった。
正章の両親は亘理町でも山側に住んでいたため、特に被害を受けることはなかったのだが、仙台市内の海側にある東北農業大学の大学院研究室と実験農場は大きな被害を受け、これまでその片付けに追われており、ようやく今日から、次の研究のためのディスカッションに入っていたのだ。
正章は提案する。
「亘理の地に苺栽培を、特に亘理特産種である“わたりっこ”を復活させるためのプロジェクトを立ち上げましょう。」
その提案に、研究員の誰もが賛同し、それからの正章は、日夜仲間たちとディスカッションを続けていた。
「図らずも、我々が研究してきた水耕高設栽培の新技術を、復興のために生かせる時が来たのかも知れない。」
しかし、今回は誰も経験したことのない未曽有の規模の災害であり、土壌が海水に侵されてしまった津波被災地での農業の復興が、容易な事業でないことは十分に予測される。
彼らの研究は、当然のことながら社会が平常通りに動いていることを前提として進められてきたのだ。
殊に今回は、原子力発電所事故による放射線の農作物への影響という、我が国がかつて経験したことのない未知の分野、しかも農業学者の専門分野ではない世界が深く関わってくるのである。
それでも、この地に生まれてきた者に課せられた使命として、それをやり遂げなければならない。
正章は気持ちを引き締めている。
(つづく)