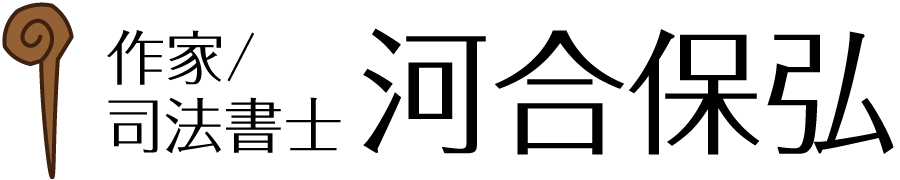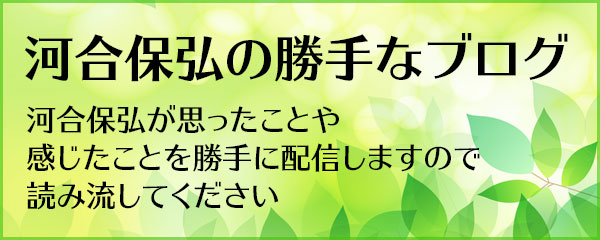震災復興&歴史発掘ファンタジー
「ストロベリーランナー ~亘理伊達開拓団からのメッセージ~」
第10回:避難所
2011年4月。
大震災が去っても、人々の恐怖が終わることはない。
毎日のように続く小刻みな揺れ、夜ごとに鳴り響く地震警戒警報、時には突然に大きな震度の余震が来て、避難所で暮らす人たちは、否が応でも3.11の恐怖を思い起こさせられる。
さらに僅か70キロ程しか離れていない場所にある東京電力福島第一原子力発電所の事故が、恐ろしい映像と共に日夜報道され、“放射線量”という今まで聞いたこともなかった忌まわしい用語が何度も繰り返されて、言い知れない暗く深い恐怖を、さらに増幅させるのだ。
両親を一瞬にして亡くした斎藤信幸は、避難所とされている中学校の体育館の片隅で、何も手に付かない日々を漫然と過ごしている。
数日前までは、両親以外では唯一の身寄りである、幼い頃から可愛がってくれていた南三陸に住む叔父夫婦が、今は行方不明ということで一縷の望みを残していたのだが、一家全員が遺体で発見されたという報せを受け、これで本当に天涯孤独になってしまったと、信幸はさらに絶望の淵に落ちてしまった。
行方不明とはなっていても、実際に戻ってくる者はごく稀であり、信幸も叔父一家のことを本当は諦めていたのであるが、それでもいざ訃報を耳にしてしまうと、そのショックは決して小さいものではないのだ。
大雄寺で負った自分の足の傷は日々回復しつつあるが、生き残った自分だけが恵みを受けているように思えて、それがかえって悔しい。
「もしあの時、電話が母ちゃんに通じていたら・・・」
3.11、柴田里美が自分の両親に電話した後に、腰を抜かして倒れている信幸に代わって母に電話を掛けてくれたが、タッチの差で通じなかったことを思い出す。
もちろん、電話が通じていたら両親が必ず助かっていたという保証などありはしない。
実際、逃げようとしても逃げ遅れてしまった人たちは山ほどいるのだ。
それでも、自分があの時、自らで母に電話をすることができていたなら・・・。
しかし、その時には恐怖と痛みとで、何も考えることはできなかった。
そんな自分自身の弱さを、信幸は責め苛む毎日である。
そして、目を閉じる度に、大雄寺から見たあの恐ろしい光景を、何度も何度も思い出してしまうのだ。
これも、信幸に限らず、多くの被災した人たち、希望を失ってしまった人たちに共通する現象なのであろう。
一方、里美は信幸とは全く逆に、司法書士の桜木司織と共に、進んで避難所の仕事を手伝ったり、困っている人の相談を受けたりして、我を忘れたかのように精力的に働いている。
避難所には、誰かがやらなければならない仕事は、探しさえすれば無限にあるのだ。
阪神大震災での経験を生かし、常に冷静に皆のことを考え、献身的に動く司織の影響もあるのであろうが、里美にとって大雄寺で見た恐ろしい光景を忘れていられる時間を少しでも作りたいという気持ちが、最初の頃には確かにあった。
しかし、徐々に自分に与えられた使命、すなわち無事に生き残った者たちに課せられた役割というものに、里美は気付き始めつつあるのかも知れなかった。
里美は、一人になってしまった信幸の世話をするために、信幸の居る避難所にも毎日顔を出して、何とか励まそうとしているが、何も喋ろうとしない信幸との間に、冷たい溝が出来つつあることを感じていた。
震災前夜に受けた信幸からの告白に、まだ里美は答えてはいなかった。
もちろん、今はそれどころではない。
そんな中でも、両親を亡くした幼馴染である信幸を、そのままに捨て置くことはできなかったのだ。
しかし、信幸の頭の中には、仲間の中で自分だけが、一瞬にして両親も家も仕事も、さらに全ての身寄りまでもを根こそぎ失ったという、言葉にできない恨みつらみがある。
そのことからか、3.11、あの時一緒に居たというのに、無傷で一見は元気そうに見える里美の姿を無意識に妬んでいる、そんな自分自身の弱さ脆さへの苛立ちがあった。
(つづく)

※避難所です。かなり後の時期の写真ですが。