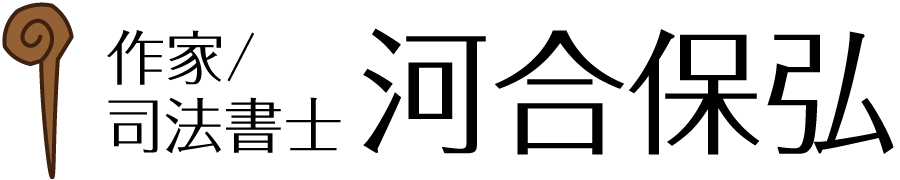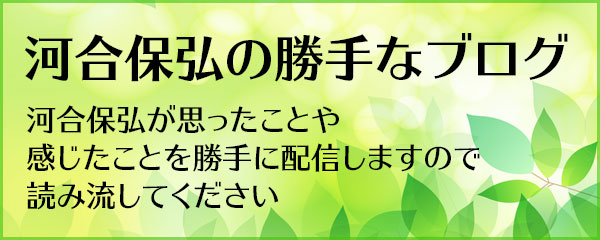震災復興&歴史発掘ファンタジー
「ストロベリーランナー ~亘理伊達開拓団からのメッセージ~」
第4回:繁爺が畑
収穫の時期を迎えた亘理町の東側、海に近い浜吉田地区にある苺畑、通称“繁爺が畑”では、経営者の千草繁明と東北農業大学の大学院で研究員になっている田村正章が激論を交わしている。
皆から“繁爺”と呼ばれて親しまれている繁明は今年で66歳、亘理名産の新品種の苺“わたりっこ”の開発者の一人であり、有力な生産者でもある。
正章は言う。
「これからは合成養液を使った水耕栽培の時代ですよ。」
しかし、繁明は取り合おうとはしない。
「苺は大地から栄養を貰って育つものだ。」
「これからの苺農家は高齢化するので、高設栽培で足腰への負担を軽くできます。」
「苺を立って収穫するなんて、苺に失礼だ。」
「繁爺だって、年なんだから、いつまでも畑仕事、できないでしょ?」
「それとこれとは話が別だ。」
二人の議論は全く噛み合わず、いつまでたっても言い合いは終わらない。
そこに村山広絵たちがやってきた。
「あら、正章さん。」
広絵の言葉に柴田里美が突っ込む。
「どうして正章だけ“さん付け”なのよ。」
「い、いえ、役場で会うことがあるし、呼び捨てじゃマズいから・・・。」
どうやら広絵には、正章に対して何かしらの感情があるみたいだ。
正章は、事情を知らない様子の斎藤信幸と里美に対して言う。
「僕は今、大学院で苺の水耕高設栽培の実用化の研究をしていて、繁爺に技術の説明に来ているんだけど、爺さん頑固でね。」
水耕高設栽培とは、ビニールハウスの中に高さ1メートルくらいの水路を張り巡らせて、そこで苺を栽培するという技術で、この方法を使えば年間を通じて安定的に苺を生産でき、かつ収穫する者の足腰への負担も軽減されるという。
事情を知ってか知らずか、里美は天真爛漫に言う。
「繁爺に先端技術の話をしたって無理なんじゃないの?」
信幸は、この場の雰囲気を察したのか、あるいは天然なのか、見事に実っている苺の実を見ながら、ここで口を挟む。
「それより繁爺、今年の苺、とってもイイ感じじゃんね。クリスマス商戦でいっぱい売れそうだな。」
正章も機嫌を直して言う。
「雄太も誘っといたよ。みんなで“わたりっこ”食べるかって言ったら、すぐ飛んでくるって。」
「“日本一の漁師”も亘理の苺には目がないってことか。」
里美の言葉が終わる頃、坂口雄太が到着した。
雄太は声を弾ませて言う。
「みんな、喜んでくれ。ついに俺の船を買えることになったんだ。3月の初め頃には港に来るぞ。」
繁明を含め、全員が拍手喝采で雄太を祝福する中、信幸だけは少し複雑な気持ちだった。
信幸と雄太は、幼いころから何故か同じものを欲しがる傾向があって、お菓子の取り合いから恋人の取り合いまで、ずっとライバルだったのだが、雄太がいよいよ“俺の船”を買い、一人前の漁師になると知って、ますます大きな差を付けられてしまったと感じていたのだ。
しかし、暫くぶりに集まった昔の同級生たちは、楽しそうに互いの顔を見合わせている。
「よし、みんな揃ったところで、今年の“わたりっこ”試食会といくか。」
繁明が声を掛け、摘み取ったばかりの“わたりっこ”を皆で分け合う。
先ほどまで言い合っていた繁明と正章も、今は楽しそうだ。
「“わたりっこ”、今年は特に出来がいいから、東京の人たちも喜ぶと思います。」
広絵の言葉に、全員を子どもの頃から知っている繁明が、手近にあった苺の茎を手に取りながら、しみじみと言う。
「そうだな。それにしても皆、この苺みたいに見事に育ったもんだ。」
誰もが明日の亘理の発展と、自分たちの明るい未来への希望に満ちた、微笑ましい収穫の時期のことであった。
(つづく)