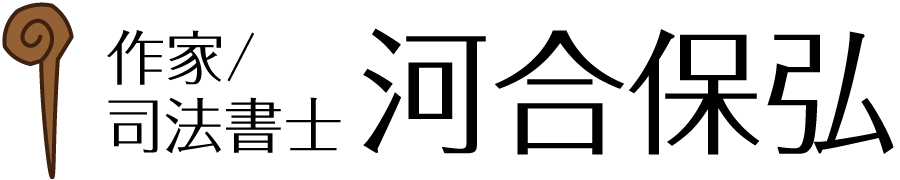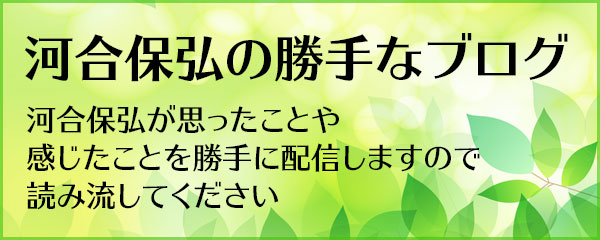震災復興&歴史発掘ファンタジー
「ストロベリーランナー ~亘理伊達開拓団からのメッセージ~」
第3回:成長
2010年12月。
あれから15年、小学生だった子どもたちは、それぞれに大きく成長した。
亘理町役場の商工観光課に勤務する村山広絵が、町役場の車で亘理町の東側、太平洋に面した汽水湖である“鳥の海”の前に建つ町営施設“わたり温泉鳥の海”でアルバイトをしている柴田里美と、鳥の海に近い荒浜近辺にある両親が経営している苺畑で働く斎藤信幸を拾って、やはり海沿いの浜吉田地区にある千草繁明(ちくさ・しげあき)の苺畑、通称“繁爺が畑”に向かっている。
広絵は、来年3月14日のホワイトディに予定されている、地元の農業協同組合が主催し、町役場の商工観光課が協賛する、亘理名産の独自品種の苺“わたりっこ”の東京駅前でのキャンペーンに、幼馴染の里美と信幸とを参加させようと思っていたのだ。
この三人と田村正章、坂口雄太は、小学校から高校まで一緒に進学したが、幼い頃からの希望通りストレートに亘理町役場に就職した広絵と、予定通りに漁師になった雄太以外は、この8年くらいの間で、それぞれに運命が分かれてきている。
信幸と正章は一緒に東北農業大学を受験したが、正章は合格して大学院まで進み、今やエリート研究員なのに、信幸は不合格で、何年か浪人した後は受験を諦めて、その後は荒れた生活を送っていた。
今は何とか立ち直って実家の苺畑を手伝ってはいるが、不合格から8年たっても優柔不断でウジウジした性格が治らないままのようだ。
里美は高校卒業後、両親や友人たちの反対を押し切って、小学生時代の夢を思い出したのか、女優になると宣言して東京に行き、何年間かは劇団に所属していたようなのだが、2ヶ月ほど前に亘理に舞い戻ってきて、今は時々実家の食品工場を手伝ったり、いろいろな場所でアルバイトをして日々を過ごしている。
一方、里美の姉の支倉智美(はせくら・ともみ)は、東京の有名女子大を卒業後、仙台の放送局に就職して、今はレポーターなどの仕事をしており、一昨年には有名建築家の夫と結婚、仙台市の海沿いに立派なマイホームを建て、間もなく第一子が生まれるという、まさに幸せの絶頂に居るので、姉への嫉妬羨望が里美の中で渦巻いていることは間違いない。
幼馴染の広絵の思いは、信幸には亘理で開発された苺の独自品種である“わたりっこ”生産者としての誇りを持たせること、里美には敢えてキャンペーンの主役を任せることで自信を持たせて、もし可能であるなら姉妹の関係を改善できればとのことであった。
“東北の湘南”と呼ばれる通り、亘理の冬は東北の他の地区に比べると温暖だ。
大きなマスクに眼鏡と帽子、そしてコロコロした厚着の広絵に対し、里美は明るく言う。
「広絵ちゃん、車の中なのに、どうしていつもそんな完全装備なの。ちょっと浮いてるよ。」
里美の明るさの裏側にある憂鬱を十分に分かっているつもりの広絵だが、容姿に自信のない自分が、心の何処かで里美と智美という美貌に恵まれて生まれてきた姉妹にコンプレックスを感じていることも分かっている。
「私は里美ちゃんと違って、顔に自信がないからさ。キャンペーンも“ワタリ姫”の着ぐるみで行くわ。」
広絵の、そういった少しだけ僻みの気持ちが入った言葉には、天真爛漫な性格らしい里美は気付かないようである。
女性二人に囲まれて信幸は何も言えないが、実は里美のことが以前から好きで、彼女が亘理に帰ってきて以来、ずっと告白するチャンスを窺っているのだ。
しかし、里美の方は信幸のことを、単なる幼馴染の頼りない友人の一人としてしか思ってはいない。
「信幸ったら、苺の収穫で屈んでばかりで腰が痛い痛いって、ホント年寄りみたいで情けないわ。もうちょっとしっかりしてよね。」
広絵が言う。
「繁爺なんて、あの歳でも平気であれだけの畑を一人で収穫してるんだからね。やっぱり昔の人は、信幸なんかとは根性が違うわ。」
「そう、今の男の子たちは、根性が足りないのよ。」
「いいえ、雄太なんて今や立派な漁師さんだよ。信幸が頼りないだけだと思うわ。」
「そうね、正章は立派な学者さん、みんな小学生だったの頃の夢を着々と叶えているのにね。」
坂口雄太や田村正章という、信幸にとってはライバルとも言える名前を次々に挙げて褒めたたえる里美と広絵の言葉は耳が痛いが、気の弱い信幸は、何も言い返せない。
本当は自分も、曲がりなりにも小学生だった頃の夢の通り「いちごを作る人」にはなっているのだが。
そう言っているうち、車窓に「繁爺が畑」が見えてきた。
(つづく)